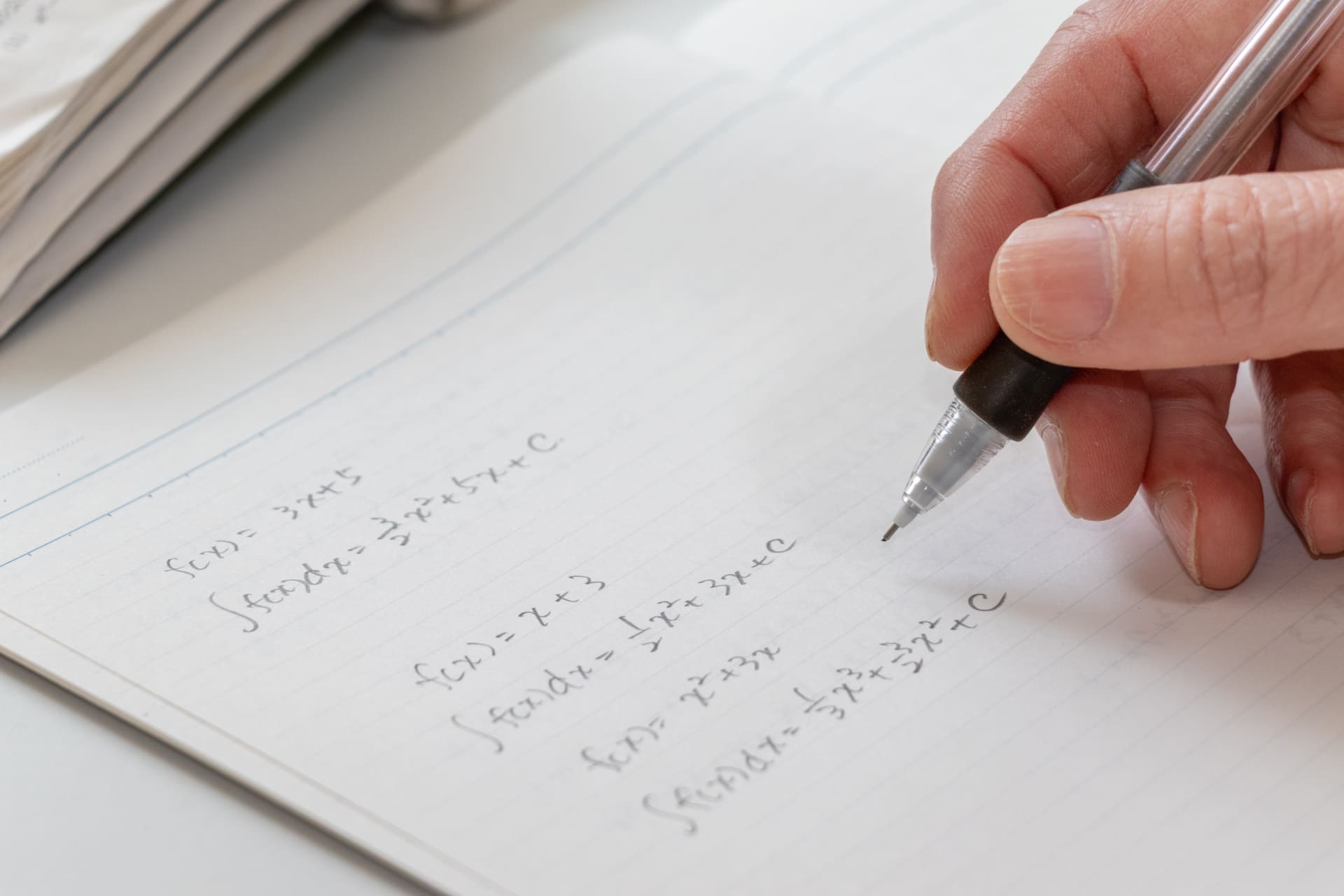
ノートの取り方ひとつで、勉強の理解度や成績に大きな差がつくことをご存じでしょうか。授業をただ写して終わるのではなく、自分なりに整理されたノートを作ることで、記憶への定着や復習の効率が大きく変わります。見やすく、振り返りやすいノートは、勉強を継続するモチベーションにもつながります。
この記事では、ノートの取り方が勉強にどのような影響を与えるのかをはじめとして、授業中の工夫、復習に強いノートづくり、科目別のポイント、そして紙とデジタルの使い分け方まで、効果的なノート活用の方法を詳しく解説します。自分に合った方法を見つけ、学びをさらに深めていきましょう。
ノートの取り方が勉強に与える影響
ノートは単に授業内容を写すだけのものではありません。上手に取ることで、記憶の定着や理解の深まりに大きな効果をもたらします。視覚的に整理されていると後で見返しやすく、学習効率を高める重効果も。ここでは、ノートの取り方が勉強全体に与える具体的な影響について見ていきましょう。
記憶に残りやすい
まとめ方によって、記憶への定着率は大きく変わります。脳は、受け取った情報をどのように処理するかで記憶の深さを判断するもの。そのため、授業内容をそのまま書き写すだけでは受動的な作業となり、記憶には残りにくくなってしまいます。
しかし、自分の言葉で要点をまとめたり、図解や色分けを加えたりすることで、情報を「整理して再構築する」という能動的な働きが生まれます。このプロセスを経た情報は、脳にとって「重要な内容」と認識されやすく、記憶にも残りやすくなるのです。
ノートをとる行為そのものにも、記憶強化の効果があります。手を動かして書くことで、視覚・聴覚・運動感覚が連動し、脳の複数の領域が刺激されます。特に紙に書く場合、指先の感覚や筆圧の違いが脳に印象づけられやすく、記憶との結びつきが深まる傾向にあるようです。
理解力が高まる
ノートを取ることは、ただ話を写すだけではありません。聞いた内容を自分の言葉でまとめることで、考えながら書く習慣が身につき、自然と理解が深まっていきます。たとえば、先生の説明をそのまま書くのではなく、自分なりに言い換えたり、ポイントを整理したりするだけでも、内容をしっかりと頭に入れることができます。
また、図や表を使って視覚的にまとめると、関係性が見えやすくなり、より一層理解しやすくなります。むずかしい内容でも、自分でわかる形に変えることで、「なるほど」と思える場面が増えてきます。
あとから読み返すときにも、自分の言葉で書かれていると、当時の理解がよく思い出せて、スムーズに復習が進みます。逆に、ただ黒板を写しただけでは「これは何のことだっけ?」と手が止まりがちに。
授業中にノートを取るときは、「あとで見たときに自分がわかるかどうか」を意識してみてください。その意識をもつだけで、内容の理解がぐんと深まっていきます。
復習の効率が上がる
どんなにしっかりノートを取っても、見返しにくいと復習の効率は上がりません。復習しやすいノートは、あとから読んだときに「何が大事か」がすぐわかるようになっています。たとえば、色分けや記号を使って重要な部分を目立たせておくと、短い時間でもポイントをしっかり確認できます。
また、まとめの中に余白を残しておけば、授業後にわかったことや先生が言っていた補足情報などを書き足すこともできます。この「追記する」ひと手間が、内容を整理し直すきっかけになり、記憶にも残りやすくなります。
テスト前など、時間が限られているときほど、どれだけ「使えるノート」になっているかが大事です。一目で大事なところがわかるようにしておけば、効率よく見直しができて、勉強もはかどります。見返す前提でノートを作ることで、勉強の成果も自然と上がっていくでしょう。
授業中に意識したいノートの取り方
授業中は限られた時間の中で、たくさんの情報が一気に流れてきます。その中で、すべてをノートに書ききろうとすると、内容を理解する余裕がなくなってしまうこともあります。大切なのは、全部書こうとすることではなく「何がポイントなのか」を見極めることです。ここでは、授業中に意識したいノートの取り方について紹介します。
大事なのは「要点をつかむ」こと
授業を聞いていると、「全部大事そうに聞こえるけど、何を書けばいいの?」と迷うことはありませんか?そんなときこそ意識したいのが、「要点をつかむ」ということです。すべてをそのまま書き写すのではなく、先生が強調した言葉や何度も繰り返して説明した部分に注目することがポイントです。
たとえば、「ここはテストに出るよ」と言われたら、それは確実に押さえておくべき内容ですし、「つまり~ということです」とまとめられた部分も重要です。話の流れをしっかり聞きながら、「どこが大事なのか?」を考えながらメモをとると、自然と効率の良いノートになります。
自分なりに内容を整理して「これって、こういう意味かな?」と考えながら書くことで、理解も深まります。全部を記録するのではなく、自分の学びに必要なところを見極める力をつけていくことが大切です。
要点をつかむクセがつくと、要素がすっきりして復習もしやすくなります。「どこが核になるか」を意識しながらノートを取ることが、授業内容をしっかり自分のものにする第一歩です。
色分けや記号で情報を視覚的に整理する
ノートを見返したとき、「どこが大事なのか」がすぐにわかると、復習がとても楽になります。そのために効果的なのが、色分けや記号を使って視覚的に情報を整理することです。ただし、使いすぎは逆効果なので、シンプルにまとめるのがコツです。
たとえば、「赤は超重要なポイント」「青は補足説明」「緑は自分の気づき」など、色ごとに意味を決めておくと、ノートの見た目が整い、内容の理解もしやすくなります。蛍光ペンやカラーペンを使いすぎてカラフルになりすぎると、かえってどこが大事かわからなくなるので、2~3色までに絞ると効果的です。
また、記号も便利なツールです。「★」「→」「※」などを使って、重要な部分や理由、例などをひと目でわかるように整理できます。こうした工夫をするだけで、あとから見返したときに「どこを見るべきか」が自然に目に入るようになります。
色や記号をうまく使えば、ノートはぐっとわかりやすくなります。自分の中でルールを決めて、毎回同じ形式で使っていくと、整理されたノートを作る習慣が自然と身につきます。
余白や囲みを活かす
ノートは書いたら終わりではなく、あとで見返したときにどう使えるかが大切です。そんなとき役立つのが「余白」と「囲み」をうまく使う工夫です。これを意識するだけで、使いやすさがぐんとアップします。
まず、余白は「あとから書き足せるスペース」としてとても便利です。授業のあとに補足説明を思い出したり、先生の追加のコメントを書いたりするとき、あらかじめ余白を残しておくと安心です。特にページの横や下に空間をとっておくと、あとで追記しやすくなります。
次に、囲みを使うことで、重要なところをひと目で見分けられるようになります。たとえば、定義や公式、大事なキーワードなどを四角や雲形で囲んでおけば、復習時に自然と目に入ります。囲みを使うと、全体の印象も整理されて、読みやすくなります。
ノートは「きれいに書くこと」より、「見返したときにわかりやすいかどうか」が大切です。余白と囲みの使い方を少し工夫するだけで、もっと頼れる味方になりますよ。
復習に強いノートを作る方法
どんなにがんばってノートを取っても、復習のときに見にくかったり、どこが重要なのかわかりづらいと効果は半減してしまいます。復習に強いノートを作るには、見やすさや情報の整理がカギになります。あとから読み返したときに「わかりやすい」と感じられるような構成を意識することで、勉強効率は大きく変わってきます。
復習しやすい構成に整える
復習に向いているノートには、いくつか共通する特徴があります。そのひとつが「構成のわかりやすさ」です。情報がバラバラに書かれていると、あとで見返したときにどこを読めばいいのかわからず、時間ばかりかかってしまいます。だからこそ、ノートを取る段階で、復習のしやすさを考えた構成に整えておくことが大切です。
まず意識したいのが、見出しをつけることです。授業内容に合わせて「テーマ」「定義」「例」「ポイント」など、見出しをつけるだけで、情報のまとまりが生まれます。さらに、箇条書きや段落分けを活用すると、内容の流れがはっきりして理解もしやすくなります。
項目ごとにスペースを分けて書くことで、あとから追記もしやすくなります。ページ全体をひとつのかたまりとして使うのではなく、意味ごとに区切りをつけておくと、内容が整理されて見やすくなります。
ノートはあとで読むためのものです。見返したときに「すぐに内容がつかめる」構成に整えておくことで、復習の効率はぐっとアップします。
一目で重要箇所がわかる工夫をする
復習のときに「何が大事だったか」をすぐに見つけられるノートは、とても役に立ちます。そのためには、重要なポイントが一目でわかるように工夫しておくことが大切です。授業中や授業後に「ここは覚えておきたい」と思ったところには、マークや強調をしておきましょう。
たとえば、赤ペンでアンダーラインを引いたり、「★」や「!」の記号を使ったりすると、ノート全体の中で目立つようになります。また、公式や定義、先生が強調していた言葉などは、囲みを使って目立たせるのも効果的です。こうした工夫をしておくことで、見返したときに目が自然と重要な箇所に向かうようになります。
ページの端に「チェック欄」を作って、自分で重要度をメモするのもおすすめです。「この問題はよく出る」「ここはあいまい」など、自分の理解度を反映した書き込みがあると、復習の精度も上がります。
大事なのは、ノートを取るときから「あとで見た自分が使いやすいか」を考えることです。自分だけがわかるサインを作っておけば、復習がもっと効率よく進むようになります。
追記・まとめ直しの習慣を作る
授業中に書いたノートは、その場で理解できた内容しか反映されていません。あとから教科書やプリントを読み直したとき、「あのときは気づかなかったけど、これも大事だな」と思うことがあります。そんなときに役立つのが、追記やまとめ直しの習慣です。
あらかじめ余白を残しておけば、新しい気づきや補足情報を書き足すことができます。また、理解が深まったあとに要点を整理し直すことで、より完成度が高くなります。これは単なる「清書」ではなく、頭の中で情報を再整理する作業です。
たとえば、授業の翌日や週末に「まとめ直しノート」を作るのも良い方法です。特に定期テストの前に、これを見返すだけで全体が思い出せるようにしておけば、勉強の効率がぐんと上がります。
一度書いたら終わりではなく、何度も手を加えて育てていく感覚でノートを活用すると、学んだことがしっかりと身についていきます。追記やまとめ直しは、記憶の定着にもつながるおすすめの習慣です。
科目別!効果的なノートの取り方は?
教科によって、ノートの取り方に向いているスタイルは異なります。それぞれの教科に合ったノートの取り方を意識することで、理解しやすいようにまとめることができるでしょう。ここでは、代表的な教科ごとの工夫を紹介します。
数学は「解き方のプロセス」を段階的に書
数学のノートで大切なのは、「答え」だけでなく「考え方の流れ」をしっかり残すことです。計算式や図形の描写だけで終わってしまうと、あとで見返したときに「なぜこうなったのか」がわからなくなってしまいます。そのため、途中式や理由をできるだけ丁寧に書いて、解き方のプロセスを段階的に記録していくことがポイントです。
たとえば、問題を読んで何を求められているかを簡単にメモしたり、「ここでは公式○○を使う」と書き添えたりすることで、思考の流れが見えるノートになります。間違えた問題も、どこでつまずいたのかを残しておくと、次に同じような問題に出会ったときに役立ちます。
ページの左側に問題と式、右側に解説やポイントを書くといったレイアウトもおすすめです。見開きで原因と対策がわかるようにしておくと、復習がスムーズになります。
数学は「覚える」より「考え方を理解する」教科です。そのため、考えた過程をしっかりノートに残すことで、自分の中で理解を積み重ねることができます。
英語・古文は「本文・訳・語句」をセットで整理する
英語や古文のノートは、ただ本文を書き写すだけではなかなか身につきません。大切なのは、本文・訳・語句の3つをセットで整理し、意味のつながりを理解できるようにすることです。こうすることで、読解力と語彙力を同時に伸ばすことができます。
おすすめの方法は、本文を左側に、対応する日本語訳を右側に書くレイアウトです。行ごとに対応させて書くことで、あとで見返したときに「この表現はこう訳すのか」とすぐに確認できます。特に古文は、現代語訳を横に並べることで、文法の理解も深まります。
下のスペースに重要な単語や熟語、文法事項をまとめておくと便利です。英語なら単語の意味と使い方、古文なら助動詞や敬語の働きなどを整理しておくと、繰り返しの復習がしやすくなります。
本文・訳・語句の情報をひとまとめにしておけば、読み直すたびに「意味・表現・文法」が一度に復習できます。読むだけでなく、文のしくみを理解するためにも、ノートの構成を工夫してみましょう。
理科・社会は「図・表・用語の関係性」を可視化する
理科や社会では、用語の暗記だけでなく、「どのようにつながっているか」を理解することが大切です。そのため、ノートの中で図や表を使って情報の関係性を見える形にするのが効果的です。
たとえば、理科の授業で出てくる実験やしくみは、言葉だけで説明するよりもイラストやフローチャートを使った方が、構造がわかりやすくなります。力のつり合いや電流の流れなど、目で見て理解できるようにまとめることで、理解がぐんと深まります。
社会でも、歴史の出来事や地理の地形・気候などを表や地図で整理すると、情報の関連性がつかみやすくなります。たとえば、年表の横に人物や事件を図解することで、背景や流れが自然と頭に入ってきます。
用語をただ書き並べるのではなく、「なぜそれが大事なのか」「どんな働きがあるのか」など、説明を一言添えておくと、記憶に残りやすくなります。
理科や社会は、関係性を理解してこそ力がつく教科です。ノートの中でそれを“見える化”する工夫をすることで、より深い学びにつながっていきます。
紙とデジタル、どちらが向いてる?
ノートの取り方には、紙とデジタルという2つのスタイルがあります。どちらにもメリットがあり、自分の学び方や目的に合ったものを選ぶことが大切です。「書いて覚えたい」「スッキリ整理したい」など、自分の勉強スタイルに合わせて使い分けることで、さらに効果的な学習ツールになります。ここでは、それぞれの特徴と向いている人のタイプを紹介します。
紙ノートが向いているのはこんな人
「書いて覚えるタイプ」や「手を動かしながら考えたい」という人には、紙のノートがぴったりです。紙に手書きすることで、視覚だけでなく手の感覚や動きも使うため、記憶に残りやすくなるという特徴があります。また、自由に書き込みができるため、図を描いたり、余白にメモを加えたりといった柔軟な使い方ができるのも魅力です。
特に、数学や理科のように図や計算を多く使う教科では、紙の方がスムーズに書き進められると感じる人が多いかもしれません。レイアウトも自分で自由に決められるため、自分好みに作れるのも紙ならではの良さです。
スマホやタブレットだとつい他のアプリを開いてしまうという人にとっても、集中力を保つための手段になります。目に見える形で「自分だけの勉強の記録」を積み重ねていけるのも、達成感につながります。
「とにかくシンプルに」「自分の手で残したい」という人は、紙ノートを活用することで、自分の学びをしっかりと形にしていけるでしょう。
デジタルノートが活躍するシーンは?
デジタルノートは、効率よく整理したいときや、情報をまとめて管理したいときにとても便利です。たとえば、複数の教科を一つのアプリで管理できたり、ノート内をキーワードで検索できたりと、紙にはない機能がたくさんあります。授業の板書をタブレットで撮影して保存し、そこに自分のメモを加えるといった使い方もできます。
コピー&ペーストができるので、繰り返し使う内容を何度も書き直す必要がありません。間違えてもすぐに修正できるため、作成にかかる時間を短縮できるのも大きなメリットです。図や写真を貼り付けたり、録音した授業の音声を一緒に保存したりと、学習の幅も広がります。
特に、たくさんの資料を扱う社会や理科、長文の読解や英単語の暗記においては、整理や検索のしやすさが役立ちます。クラウドで保存すれば、家でも学校でも同じものが見られるのも便利なポイントです。
情報をまとめて管理したい人や、作業効率を重視したい人には、デジタルノートが頼もしい相棒になります。
紙とデジタルを併用するならどう使い分ける?
紙とデジタル、それぞれのメリットを活かすために、併用するという方法もおすすめです。大切なのは、自分の目的や勉強スタイルに合わせて「どちらを、どんなときに使うか」を決めることです。
たとえば、授業中は紙で手を動かしながらメモをとり、理解を深める。その後、復習用にデジタルで内容をまとめ直せば、きれいに整理された記録が残ります。紙で「考える」、デジタルで「整理する」と分けて使うのは効果的な方法です。
英単語や用語の暗記には、アプリを使ってクイズ形式にすることで、スキマ時間の活用もしやすくなります。逆に、数学や図を多く使う教科では、やはり紙に書く方がスムーズに学べるという人も多いでしょう。
一つにこだわらず、目的に応じて使い分けることで、それぞれの長所が活きてきます。「どちらか」ではなく「どう使い分けるか」を意識して、自分にとって一番使いやすいスタイルを見つけていきましょう。
まとめ
ノートの取り方は、学習の効率や理解度を大きく左右します。ただ書き写すのではなく、自分にとって見やすく、あとから復習しやすいノートを意識することが大切です。授業中は要点をつかんで記録し、色分けや囲みを使って視覚的に整理することで、理解と記憶の助けになります。また、科目ごとの特性に合わせた工夫を取り入れることで、より効果的なノートが完成します。
紙とデジタルのどちらを使うかは、目的やスタイルに応じて選びましょう。両方を使い分けることで、それぞれのメリットを活かすことができます。ノートは「とること」そのものが学びのプロセスです。自分に合った方法で、学びを深めていきましょう。








